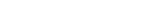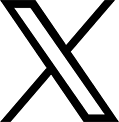ウェブメディアだけではなく、テレビや新聞でも大きく取り上げられ、注目を集めているGoogleの中国撤退。今回は、一連の騒動の経緯、中国での反応、何がどこからどう撤退するのかまとめていきたいと思います。
■ 検閲問題、サイバー攻撃、そして中国での事業撤退
はじめに、先日発表された「Googleの中国撤退」に至るまでの経緯を追ってみましょう。
Googleは、2006年1月に中国でサービスをスタートしました。中国における検閲の問題は周知の事実、Googleの提供する検索エンジンもこれに漏れず、「天安門事件」「ダライ・ラマ」といったキーワードに対してフィルターがかけられ、検索結果は限られたものとなっていました。中国で表示される検索結果については、米中での検索結果をスクリーンショットで比較した次のエントリーが参考になります。
▽ らばQ:中国版Google「天安門」の検索結果が海外で話題に、外国人たちのコメントは…
検閲の問題が存在する一方で、三億人を超えるインターネット人口を抱えるとも言われる中国に魅力があるのも事実。同社は検閲を受け入れながら検索サービスを提供してきました。このような平衡状態が4年ほど続きましたが、2010年のはじめにGoogleは中国からのサイバー攻撃を明らかにし、これまで検閲に基づいてフィルターしていた検索結果を表示するようになりました。
▽ 遂に「天安門事件」が検索可能に Googleが中国政府の検閲に抵抗 - はてなブックマークニュース
▽ そら速: マジギレGoogle△「天安門事件の写真、中国で閲覧可能にしてやったわ!どや!」
また、このサイバー攻撃について、背後に中国当局の存在を指摘するエントリーもあります。
▽ Googleへのサイバー攻撃、攻撃元は中国当局だった - スラッシュドット・ジャパン
こうして、継続的な検閲要求に業を煮やしたGoogleがサイバー攻撃をきっかけに、中国での事業撤退まで示唆するようになったととらえることができそうです。これに対して、中国当局はGoogleへのアクセスを遮断して対抗、政府高官まで巻き込んだ交渉がすすめられましたが、現在報道されている中国撤退の決断に至ります。
一連の出来事をより深く追ってみたい方には、サイバー攻撃の手口まで詳述しているGIGAZINEのエントリーがおすすめです。
▽ Googleと中国政府との検索結果検閲問題、一体何がどうなって香港へ移動することになったのかまとめ - GIGAZINE
■ 中国での反応
一方の中国はというと、Googleの発表から数日、当局はあくまで強気のようで、以下のような反応が出てきています。
▽ 中国が検閲回避を表明した Google を公式に非難 - japan.internet.com Webビジネス
▽ グーグル撤退 中国、国産サイトで統制 : ニュース : ネット&デジタル : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
今回のGoogleの対処を「完全に間違っている」と非難するとともに、国産のサービスで対抗していく構えもあるようです。また、現地からユーザーの反応を紹介したエントリーも。
▽ 【山谷剛史のマンスリー・チャイナネット事件簿】 Google撤退〜中国国内は報道少なく、超ヘビーユーザーはtwitterで抗議 -INTERNET Watch
老舗のポータルサイトでのアンケートでは「撤退してほしくない」という人が大多数で、一連の騒動に関するブログでの議論はほとんど見当たらないものの、「金盾(※筆者注:中国の検閲システム)をくぐり抜けられる少数派の超ヘビーユーザーらは、twitter上で現状と将来を嘆いているようだ。」と締めくくられています。
■ 結局どうなる?
Googleの今後の対応についてはさまざまな情報が入り乱れていますが、公式ブログのエントリーが参考になります。
▽ Official Google Blog: A new approach to China: an update
Google.cnでのウェブ検索、画像検索、ニュースサービスは既に打ち切られ、Google.cnにアクセスしたユーザーは香港のサーバーを介して提供されるGoogle.com.hkへリダイレクトされるとのこと。中国での各サービスの利用可否については以下のページで情報提供されています。
▽ Mainland China service availability
また、業務については、研究開発と営業に関しては現地で継続する意向があるようです。
Googleの発表から数日、まだ先が見えない状況ではありますが、インターネットが普及してはじめてとも言える規模の政府まで巻き込んだ議論と展開、今後もしばらく目が離せなさそうです。
The photo by phauly.