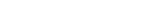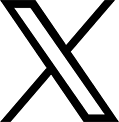鳥類の一部は、鳴き声を介して他の個体とコミュニケーションをとることが知られていますが、これまで鳴き声の“並び”に意味があるのかは不明でした。京都大学大学院生命科学研究科の安部健太郎助教、渡邉大教授らのチームは6月27日(月)、ジュウシマツを用いて、鳴き声の並びに意味があることを明らかにしたと発表しました。
▽ 鳥類の音声シーケンス情報処理能力の解明 — 京都大学

▽ http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20110626-OYT1T00718.htm

京都大学のホームページによると、「ジュウシマツには鳴き声の並びを識別する能力があること」「ジュウシマツは鳴き声の並びを識別する能力を後天的に獲得している可能性があること」などが明らかになったそうです。また、鳴き声の並びを識別する際に用いられる脳内の神経領域も突き止めたとのことです。
はてなブックマークのコメント欄には「おもろいね。意味はどれくらいあるんだろうなあ」「単語に類する鳴き声、さえずりは多くの動物に見られるが、文法に類する物が見られたという奴だな。文法に方言があるかは気になるところだ(w」といった感想が寄せられています。
研究成果は、「Nature Neuroscience」のオンライン速報版に「Songbirds possess the spontaneous ability to discriminate syntactic rules」というタイトルで掲載されています。
動物の言語に関しては、独立行政法人 理化学研究所の岡ノ谷一夫さんも以前から研究しており、「言語の起源」や「ジュウシマツの歌の文法構造」に関する記事がはてなブックマークで注目されていました。
▽ http://www.riken.jp/r-world/info/release/news/2009/nov/frol_01.html