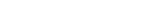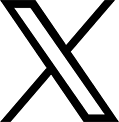大分県別府市の山の上に、「立命館アジア太平洋大学(APU)」という名の一風変わった大学があります。キャンパスにいる学生と教員の半分が外国人という大学に、Webサイト「ほぼ日刊イトイ新聞(ほぼ日)」を主宰する糸井重里さんが注目。ほぼ日が大阪・梅田で開催したイベント「はたらきたい展。」の一環で、APUの副学長を務める今村正治さんと糸井さんが「はたらく場所はつくれます論」というタイトルのトークショーを開催しました。“無謀”なプロジェクトで自身が働く場所を作ったという今村さんの話から、働くことについて考えます。
■ 究極の国際大学を、大分県の山の上に作る
APUは、立命館大学100周年の記念事業で生まれた“究極”の国際大学です。「50ヶ国以上から学生を集める」「学生の50%は留学生」「教員の50%は外国籍」という「3つの50」をコンセプトに、2000年に開校。現在は、約80の国と地域からやってきた留学生と日本人が約半数ずつの比率で学んでいます。
今村 立命館大学は1994年、滋賀県草津市に「立命館大学 びわこ・くさつキャンパス」という大きなキャンパスを完成させました。お金を使い果たして、勘弁してくれという状況の中、大分県と別府市から熱心な誘致があって、1994年9月にAPUを作ることが決まったんです。当時、私は学生部というところで働いていて「はぁ?まだやるのか」と。
糸井 ヘトヘトだったのに。
今村 はい。どんなところに大学を作るんだろうと思い、現地に行ってみたら、標高約400メートルの山のてっぺんに草原があって「そこです」って。原野商法という言葉が頭をかすめました。
会場 (笑)
糸井 僕も行きましたが、霧が深くて前が見えないくらい高いところ。
今村 山の上に大学を作るだけでも大変なのに、半分が留学生というコンセプトからして、難易度の高い低いを超えている状況。留学生の募集は従来、海外や日本の日本語学校を回って声を掛けるんですが、APUは日本語が一切できなくても、英語だけで入学できる大学にしたかったんです。ですから、とにかく海外に直接募集に行かないといけなくて。わかりやすく言えば、ある日職員と教員が部屋に集められて「君たちはこの国。はい、行ってらっしゃい」という感じで担当が決まって。
糸井 割り当ての中にはアフリカとかもあるんですよ。
今村 私の担当は主に韓国で、開校までに何度も渡航して、現地のスタッフと高校を100校ほど回って説明会をしました。開学前後の訪韓は150回を超えると思います。韓国事務所も立ち上げました。みんなそんな経験がゼロだから誰にも相談できないし、「行け」と言う上司もどうしていいか分からない。前例がない中でどうするか。自分がやるしかない。でも、やってしまえば自分が“専門家”なんです。
糸井 嫌だと思わなかったんですか?
今村 思わなかったですね。APUの事務局ができたとき、私はどちらかというと野党的で「こんなの作ったら失敗するぞ」と批判していたんです。でもね、本当は、興味はあった。だから「APUの仕事をやらないか?」と言われたときは、喜んで行きました。大学という経営体は、学生が学費をきちんと払ってくれれば、めでたしめでたしなんです。日常のサイクルが永遠に続けば、大学は潰れない。「入学式だなー」とか「卒業式だなー」と言っていれば、1年が終わる。
糸井 穏やかだね。
今村 そう、穏やかです。それが1994年のびわこ・くさつキャンパス開設あたりから破られちゃったのかな。外界との結び付きが増えて、チャンネルが増えていくと、いろんな“やってみたい”という気持ちが出始めるんですね。APUのことも、大学を作るなんてことは100年に一度あるかないかの大仕事だから、苦労してでもやりたい気持ちがみんなにあったと思います。

糸井 集められた職員と教員の心はそろってたんですか?
今村 教員、職員それぞれ100人ずつから始まったプロジェクトですが、心はそろっていたと思います。今思えば不思議な話です。みんなが力を合わせて、新しいものを生み出した。
糸井 ビジョンがくっきり見えていたわけじゃないのに、そろう仲間がいたというのが面白い。
今村 社会性という面から見ると、教員が持つ“バランス”はいろいろな意味であまりよくないかもしれない。だけど、彼らは絶えずユニークな仮説を考え、何かに迫ろうといつも研究している。こういう構想力を持った教員の力がなければ、大学は発展しないんです。職員の力だけでは無理です。
糸井 つまり集団的なビジョナリストがいたから、面白いという気持ちをかき立てることができた。
今村 そう。仮説を証明するのが研究だとしても、例えば「雨の降る日は天気が悪い」という仮説を証明しても面白くともなんともない。大胆な仮説で常識に挑戦するから面白い。APUの構想が走りだしたころは、私自身もうまくいくという自信はなかった。しかし当時の経営のトップは、大分県や別府市から多額の支援をしてもらったり、企業を回ったりして40億円以上の寄付を集めた。そういう努力をコツコツとやっていました。
糸井 相当のトップセールスですね。
今村 理事長は“平成の托鉢僧”だと言われてましたからね(笑)。APUの構想には、反対もありました。誰だって「大丈夫か?」と思いますよ。だけど、大分県と別府市から「ちゃんとバックアップするから来てほしい」と言われて。お金の心配が当座なかったことは大きかったです。
糸井 当座、はない。
今村 大学は完成したら終わりじゃなくて、ずーっと続けなくちゃいけない。だから、あの山の上で続くのか?という心配はありました。いつまでも学生が通って来てくれるのかと。
糸井 その学生にまだ会ったことがないですもんね。
今村 「立命館大学」は日本ではだいたい知られていますが、海外ではほとんど知名度がないから、素直に信用されるわけではないんです。詐欺じゃないかと言われたこともあります。ですから、1期生はフロンティアですよ。聞いたことも行ったこともない場所に、海外から来てくれたんですから。
糸井 その国の教科書には、東京くらいしか載ってないですよね。
今村 載ってないですね。アフリカから来たある学生はだまされたと思ったらしいです。だって、駅を降りたら洗面器持ったおばあちゃんが歩いてるんですよ。ケニアの都会っ子がみれば、温泉街・別府は田舎ですから。
■ 面白いと言ってくれる味方、NOと言って止めてくれる存在
APUのプロジェクトがスタートし、今村さんは別府市に居住地を移します。薬局の2階に「大分・別府事務所」を構え、県庁や市役所と毎日のようにミーティングを重ねます。スタッフたちは、学生を集める、建物を作る、制度を決める、カリキュラムを組む、先生を呼ぶ、説明会を開いて別府市民に理解を求める――。日常のサイクルから外れた規格外のプロジェクトが、たくさんの仕事を生みました。企業と大学の違いから、儲(もう)けることと仕事の関係性を語ります。

糸井 会社だと「それでいくら儲かるの?」と必ず問いかけられますが、大学はそれがない。大学も儲けがないと困るけれど、「こんなに儲かります」という説明はいらないんです。ここが、今日の重要なテーマ。利益を出さなければならないときは、仕事が始められなくなるんです。別府の山の上にある大学で、十分に利益を出して、地元の人も学生も職員もみんな喜ぶ計画を考えても、どっかに穴がある。おそらく、めっちゃくちゃ高い学費を取らなければ、無理になる。だけど、APUでは、お金を出してくれる大分県があった。
今村 大分県と別府市の支援があったからこそできたと思います。そして、留学生のための奨学金は何百社という日本企業から40億円以上集まりました。それらが開学を可能にした大きなパワーです。でも、奨学金はフローで使いましたので、やがて底をつきました。ですから、残念ながらというか申し訳ないというか、他大学より高い学費負担をお願いしなければならなかった。なにより、多文化環境はAPUの宝ですからね。
糸井 「いただいたお金は使っちゃいました。でも、(環境は)宝ですから」という説明は、利益を中心に考える企業では言えないですよ。ほぼ日でやっている仕事の中にも、そういう仕事がいっぱいあるんです。だけど僕たちは“仕事”を生んでいるし、“仕事”をしているのも確かなんです。お金の利益は生んでいないけれど、喜んでくれる人や、コンテンツを読みに来てくれる人、勇気を得る人を生み出すということは、してる。10万、20万円の黒字を出すよりも、100万、200万、1,000万円の赤字が出て生み出したことの方が、実は多くて面白い。APUがもし営利の企業で、利益を出すことが義務という経営者だったら、クビでしょうね。
今村 クビでしょうね。まず(利益は)出ないです。日本の大学経営の収入は、学費が7割~8割。ほとんどが学費に依存してしまっている。そんな循環の経営では、新しいことは生まれません。APUは学生の半分が留学生で、奨学金をたくさん用意しなければいけない。ものすごく大きなハードルです。しかし、大きなビジョンがあって、それを面白いと言ってくれる人が大学や大学の外にもいてくれるから、成立するんです。こんなにたくさんいてくれるのかと、本当に意外でした。
糸井 そうですか。
今村 開学の構想には、ほとんどの企業が賛同してくれました。奨学金やさまざまな協力を得ることができたのです。ビジョンというのは、教育像や大学像を書き換えるぐらい大きなものであるほうがいいと思ったんですね。気取って言うとね、我々は教育を根底から変えてやるぞという気持ちがあったんです。
糸井 前提として、今まで立命館大学が築いてきた“信用”というブランド力もあると思うんです。だけど、工事の規模やビジョンの大きさからしたら、今までの立命館大学の“信用”なんてちっちゃいもんだと。
今村 ちっちゃいです。「面白い」と言ってくれる味方がひとりいないと足を踏み出せない。だから、2人目がすごく大事だと私は思います。3人目はそこからつながっていくので。
糸井 2人目が大事っていうのは基本中の基本ですよね。面白いことを考えたら、ひとり誰かに言ってみること。
今村 それともうひとつは、「NO」と止めてくれる人がいないと困る。上司と部下がいる組織だと、言える空気が大事ですよね。ありがたいことに、大学は自由なのでわりと言えるんです。立命館大学の場合、教員と職員、学部と学部の関係がフラットに近いのが、何かするときに大きいですね。
■ 寮内で“働く”学生たちが得るもの

糸井 「フラット」といえば、立命館大学にはもうひとつ、“仕事”はお金だけじゃないという素晴らしい例があります。
今村 立命館大学には古来から、先輩学生が後輩学生の面倒を見るという仕組みがありまして。
糸井 古来から(笑)
今村 学生が自治的に行っていた伝統的な仕組みに大学が目を付けて、主役は学生のまま制度化したんです。それが「オリター制度」。毎年800人弱の学生がオリターとして新入生の面倒をみます。だいたいは2、3年生。新入生はそれに感激して、次は自分がオリターをやりたいと思い、制度がつながっていくんです。
糸井 地方から立命館大学に入学して、何しようかな、分からないというときに、オリターがそっと近づいてくるんですね。
今村 そうですね(笑)。立命館大学は、大学なのにクラス(学級)があって、オリターはリーダーとしてクラスを指導して、学生生活全般の相談に乗ります。「クラスコンパやろうよ」とか「こうしたらもっと勉強できる」とか。この仕組みを、レジデント・アシスタント(RA)という制度で、APUにも取り入れました。APUには、APハウスという今では1,300人以上の学生が住む寮があります。当初は約420人収容からスタートしましたが、そのうち400人が留学生でした。普通の学生寮には住み込みの寮母さんがいたりしますが、400人の外国人と一緒に住み込みで暮らしたら、たぶん3日と持たないんじゃないかと。
糸井 そうでしょうねえ。
今村 そこで考えたのがRA。1ヶ月に2万円の奨学金を給付して、先輩学生が寮生の面倒を見る。キャンパス管理のおじさんたちがいて、大学の学生部があって、アシスタントする学生がいる。この三位一体で寮を管理しようと。しかもRAの学生たちは、寮の運営を通じてものすごく成長する。
糸井 文化が違うと、当たり前と思ってやっていることが、他の人にとって迷惑だったりする。RAは、注意しなくちゃいけないことから楽しくやっていく方法まで考える。フラットな関係なのでリーダーではなくて、楽しいお世話役。RAは “働いている”わけです。
今村 2万円でね。
糸井 2万円のことはさておいてね(笑)。2万円が欲しくないわけではないと思うけど、アルバイトだとしたら最悪ですよ。
今村 ある種の名誉というか、働きがいだと思います。もちろん、多文化環境の大学はいいことずくめではありません。寮生活ともなれば、異質性に求められる包容力は並大抵で済まない。自分のアイデンティティが崩壊するような出来事や、今までの価値観は何だったのかと問われる場面に出会うんだから。朝から晩まで「お前が言っていることは常識でないんだ!」と突き付けられるのは、すごい経験です。
糸井 そういう人が成長して、ビジネスや政治をやるときに、「お前そう言うけど、こういう人がいるんだよ」と言えるんですよ。
■ 働くことは、仕事を作ること
糸井さんが働くことについて考え始めたのは、同じスーツを着た就職活動生が、ぞろぞろと歩いて会社の中に入っていくのを目撃したことがきっかけでした。企業は言うことを聞いて、同じ服を着て、同じような答えをする人を雇っていいのか。学生は、「逆らわない」をテーマに歩いていていいのか。糸井さんは「働くってもうちょっと面白いんじゃないの」と、さまざまな角度から“働く”を考えてきたと話します。
糸井 食っていくということを、みんな恐ろしいことのように言うけど、食っていくだけなら、案外できると思うんです。でも、食っていくだけじゃ嫌だと思うのが人間だよって。もっと大きな問題が隠れていて、それを知ったときに自分は何をするか。1回組み替えて考えていくのが、テーマなんじゃないかなって思っています。
今村 実は私、ほとんど就活をしたことがなくて。立命館大学の文学部出身なんですが、就活を何もしないでぷらぷらしていて、大学院に行くか行くまいか考えていた。で、大学職員の試験を受けてみたら受かったんです。はっきり言って、ずっといる気はありませんでした。だって、子どものころから大学職員になりたいっていう人なんていないでしょ? 動機もなく始めただけです。なんで続けているのかと思うんですが、ずっと働いてきて、結局立命館大学が好きなだけなんです。
糸井 好きにさせた立命館大学が、またねえ。でも僕、今日は立命館大学の宣伝をしに来たわけじゃないんです。
今村 (笑)
糸井 僕は、“働く”は“仕事”を作ることなんだというのを、自然に思っていたんです。毎日家の前を掃いている人がいたら、それは“働く”じゃないですか。お金にはならなくても、ありがとうと思われなくても、目に気持ちがいいからやっている。“働く”って、とにかく給料じゃないよと。僕、個人も法人も、そうなっていくんじゃないかな?と思っているんです。
今村 私は、人と同じ“仕事”をしていたら、自分が働く意味がないんじゃないかと、ずっと考えています。昔、ある上司に「君に上司はいないね。自分でとっとと仕事を作ってやるから」と言われました。この間もうちのトップに「仕事を趣味に、趣味を仕事にがモットーです」とおどけて話したら、「君のはぜんぶ趣味。だけど、立命館という風土の中だからこそできることを君は知らないとダメだ」と言われました。私は、自分の力で仕事をやっているとどこかで思っていたんですが、何人かの理解者と面白がる人がいなければできなかったと気付かされましたね。
糸井 「お前が言うんだったら賛成じゃないけど手伝うぞ」という人がいるのは、働く大きな要素ですよね。みんな、机に向かってパソコンのキーボードをカタカタ打っていたり、真剣な顔をして何かを見ていたり、帳面めくってたりすることばかりを“仕事”だと思ってるけど、「お前のやること面白いな」と言ってもらえることも、実は“仕事”なんですよね。
■ 仕事の材料としての“お金”
ほぼ日と立命館大学は、東日本大震災で被災した東北地方の支援活動を行っています。日々の仕事や勉強で忙しい中でわざわざ東北に行くことの意味から、働くことを考えます。

今村 どうしてはるばる京都の大学から東北に行くのかと。
糸井 仕事増やすんだからねえ。
今村 そうなんです。でもやっぱり、学生は行ってくれます。
糸井 それこそ利益より持ち出しになるわけで。「得たものはなあに?」と聞かれたら、そこここや自分の中に満足が生まれたり、お金を使っても得られないことが得られたりしている。お金でその満足だけ買ってきてくれよとはいかないですよね。
今村 「100万円あげるから黙って座ってろ」って言われても嫌じゃないですか。苦痛ですよね、そんなこと。
糸井 僕、そんな将来が来ると思っているんです。この間、アメリカのハーバード・ビジネス・スクールの学生さんが取材に来てくれたんですけど、今みたいなことを言うと、分かってくれるんですよ。金融でどう儲けるかを考える人たちが集う、ある意味では悪名高き学校だと言われてしまうかもしれないところですよ。でも、僕らが考えていることを理解してくれる。うそで理解してるとは思えないから、こんなことが分かってもらえる時代になってきたんだと思います。アメリカでも今、学生が就職したい組織の上位に、教育を支援するNPOが選ばれている。
今村 教育という仕事はすぐ結果が出ないから、言い換えれば自分にはできないことを後世に託す、未来を託す仕事なんですよね。
糸井 四半期ごとの利益をチェックしている組織とは、想像もできない違いがありますね。「はたらきたい展。」で紹介している人の中には、儲かっていない人がいっぱいいると思うんです。でも「いいなあ」と思われている人もいっぱいいる。両方やれている人もいる。僕は、両方やれている人になりたいと思っていて。ほぼ日を始めたころ、社員に子どもが生まれて、ゾッとしたんです。関西弁で言うなら「そんなんして、ええのん?」と。零細企業をやっている人はみんなそうだと思うんですけど、「うち、子ども生んで大丈夫な会社じゃないんだけど……」という気持ちで。大丈夫にしてきたつもりですけど、やっぱり怖かったんです。でも、今は「生まれてよかったね」と言える。「よかったね」と言える状態だからこそ、“普通のこと”が考えられる。「こんなことしたい」と言われたときに、儲かると限らないことを仕事の中に混ぜていけるのは、儲かっているからなんです。APUの寄付がなかったらやれないというのも同じで、お金がなくてもやりますかと言われたら、やらないですよね。
今村 無理ですね。
糸井 まごころは武器かもしれないし、絆は力かもしれないんだけど、同じように、材料としてお金がある。ひとつじゃなくて、いろんなものが全部仕事の材料になっている。
■ 絶対に人間が必要な市場を生めるか
一流大学の講義が無料で受けられるWebサービスがブームになっていると話す今村さん。大分県まで学びに行く意味や価値を、糸井さんと考えました。
今村 自分が生身の人間としてなぜその場所で働くのか、あるいはなぜその場所で学ぶのかが、大きなテーマになっている。一流の授業がネットで見られるのは、「山の上まで来い!」と言っている僕らにとっては大変なことですから。APUでは、多文化・多言語の世界の中でリアルな息遣いを感じながら、どこの何人であろうが逃げずに対応できる人間を育てることが、使命だと思っています。
糸井 人格に及ぶような時間、というのがあの大学では流れていますよね。
今村 流れていますね。その環境をもっと磨いていくのが、大事なことだなと私は思っています。
糸井 APUには、そういうアイデアがたくさんあります。APハウスにはシェアタイプの部屋があって、外国人と日本人がセットになって住んでいる。部屋の真ん中にドアがあって、そのドアは開けていいという意思が両方にあったときだけ開くんです。韓国の学生にキムチの作り方を教わったり、日本人の食べ物を食べたり、生活空間の中で学んじゃうんですよね。文言で書いていることを暗記するというところから脱した学び。
今村 知識を吸収するというレベルではなくて、もはや稽古ですね。寝て起きる毎日の繰り返しの中に学びがある。理不尽や意味が分からないことにも直面するけど、そういうのが今、大事なんだと思っています。自分が自力で学んできた知識を持って大学に来て、仲間や教職員にぶつけてみる。まさに切磋琢磨の関係がいいんじゃないかなと。
糸井 一方で、インターネットで知識のやりとりはものすごく簡単にできるようになった。今までは人力を使わない方向に進むのが進歩だと思われていたけれど、人力を使う方向でやらないとできないものにみんなが目覚めて。手編みのセーターも、機械より目がそろってないのを嫌がってたのが今までの進歩で、「俺のために編んでくれるの……?」というのが今の価値になった。人間が絶対必要な市場をこれから生めるかどうかが、ポイントになる。
今村 そう思います。
■ 首相も社長も来る、山の上の大学

イベントの終盤には、観客から「就職活動は東京で行うことが多いが、大分からの就活という不利をどう乗り越えているのか?」「同じような大学ができて広がればいいと思っているのか、うちだけ特別がいいと思うのか?」という質問が2人に投げ掛けられました。
今村 いやあ、いい質問をしてくれました。ちょっと憎たらしいことを言います。APUには「オンキャンパス・リクルーティング」という仕組みがあります。年間数百社の企業が、うちの学生を採用したくて別府まで来てくれるんです。もちろん、東京や大阪でも就職活動をしていますが。憎たらしいでしょ?
会場 (笑)
今村 最初は、留学生が日本企業に就職するとはあまり考えていなかったんです。当時の日本社会はほとんど留学生を採用しなかったし、海外にある日本の企業に就職するもんだろうと。ところが、日本で就職したいという留学生がどんどん増えました。実際に卒業生たちの活躍ぶりを見て、企業もどんどん別府に足を運んでくれるようになりました。
糸井 僕、この間APUに行ったとき、空港で身なりのいい紳士に「糸井さんですか?」と話し掛けられたんです。名刺を渡されて、見たら、日清食品の社長だったんですよ。「どちらへ?」とは聞かなかったんですが、APUに行ったら講演をやっていて。ああいう感じで、じゃんじゃん来てくれるんですよね?
今村 コカ・コーラ本社の副社長が来たり、安倍(晋三)首相が来たり、糸井重里も来るし(笑)。ありがたいです。
糸井 もうひとつの質問が面白い。これ、僕にも聞かれたような気がします。僕の答えは「調節しています」です。自分で汗水垂らして考えたことは、やったら難しいなと思うことばっかりなんですよ。
今村 私は、まねできるものならやってみなという感じです。
会場 (笑)
今村 本っ当に大変ですから。同じ大学作るって相談されたら、勧めませんもん。韓国などでAPUをベンチマークに大学を作ろうという動きがあって、それはありがたく、大変名誉なことです。心からそう思います。目標にされるって、とても気持ちがいいじゃないですか。だけど、なかなかできないことが多い。例えばAPUでは、日本語と英語が公用語で、同じ科目を英語版と日本語版の2つ開講していて倍手間が掛かっているのですが、そのことは学校の運営、会議や文書すべてに貫かれています。また、入学式と卒業式は秋と春にそれぞれ2回ずつ、学期は4期制(クォーター制)で、これまた手間が掛かる。
糸井 APUでは、日本語を2年間で完全に話せるようにするらしいんです。“こぼれた人”のサポートが5段階ほどあって、こぼれてもこぼれても拾う。手作りというのは、こういうことだと思った。「これで日本語を覚えなかった人はいますか?」と質問しても「覚えるまでやりますから」と。
■ 今村さんと糸井さんがこれからやりたいこと
APUは2014年で開校から14年目を迎えます。人間でいうとまだ中学生と話す今村さん。“はたち”をどう迎えるかが、今後の課題だそうです。
今村 2000年のビジョンは見事な“カタチ”になったし、世界中で国際大学のベンチマークだといわれるようになりました。だけど、このまま20年続くという自信は、私には、ないです。これから、海外の大学も日本の大学も大きく変わっていきます。あの山のてっぺんにこれからずっと学生が来てくれる状況を作るには、もっといろんなことを考えないとダメだと思います。
糸井 今は中学生だけど、目線の向こう側にピッカピカの未来が見えていないと、冒険ができなくなる。冒険ができなくなったら面白くないし、面白くなかったら誰も手伝わないし、僕も見学に行かない(笑)。
今村 私は2005年に京都へいったん帰ったんですが、今年8年ぶりに大分に戻ります。華々しく開校した大学でしたが、その後学生募集に苦労した時期もありました。でも教職員が心を合わせて頑張って、私が想像していた以上にすごくいい大学になりました。奇跡といっていいと思うんです。だけど、それがいつまでも続くわけではない。今は山の上まで登ってきてくれるけど、それが未来永劫続きますとは言えない。APUは将来、卒業生によって支えられる大学になってほしいと思っています。さっきも言いましたが、日本の大学は収入の7割~8割を学費に依存しています。つまり、お父ちゃん、お母ちゃんのお金で食っていて、残念ながらそれをよしとしている。アメリカの大学は、収入に占める学費の割合は2割~3割で、あとの7割は寄付・基金運用なんです。この構造が、日本ではまだ実現できていない。卒業生たちが「僕はAPUに世話になった」「APUがあったから今の自分がある」「だから母校を助けたい」と思うような大学にしたいです。お金の問題だけじゃなくて。
糸井 「もっとよくしてください」ということですよね。
今村 そうです。それが本格的に行われる大学になれば、もう一歩次の飛躍があるのかなあと。
糸井 僕も、今村さんが考えていることとそっくりなことを考えています。ほぼ日でも連載しているんですが、トリマーをしながら愛護センターからボロボロの犬猫を引き取って、里親を探している面白い人がいて。トリマーの仕事で稼いだお金は、保護センターから犬猫を引き取る原資になって、その人のやり方に賛同した人がボランティアや寄付など、いろんな手伝いをしてくれる。僕は彼女と一緒に、犬を売らない、あげちゃうすごくきれいなお店をやろうと思っていて。ボロボロのところは、やっぱり嫌じゃない。ピッカピカで、ボランティアが楽しそうに働いていて、腕のいい病院が併設されていて、ペットホテルもやって。先輩が寄付するという話と同じです。「犬や猫にお世話になったから、私この子のお世話するわ」と。利益が目的じゃなくて、そのことが盛んになっていくことが大事なんです。捨てる人がいて、どんどん死ななきゃいけない命があるのは、同じ平面に住んでるとちょっと苦しい。だけど、ちょっと楽になるじゃないですか、一般の人も。
いいことの運動が今までできなかったことと、稼ぐばっかりの人たちがやらなかったことの、真ん中の領域があると思うんですよね。そこに、人材がものすごく欲しいと思う。
▽ 立命館アジア太平洋大学 - 立命館アジア太平洋大学
▽ はたらきたい展、開催! - ほぼ日刊イトイ新聞